潜在保育士とは? 復帰しない・できない理由や復帰の取り組みについて
「待機児童問題の背景には、単に保育の受け皿が少ないというだけではなく潜在保育士が多いことが課題である」
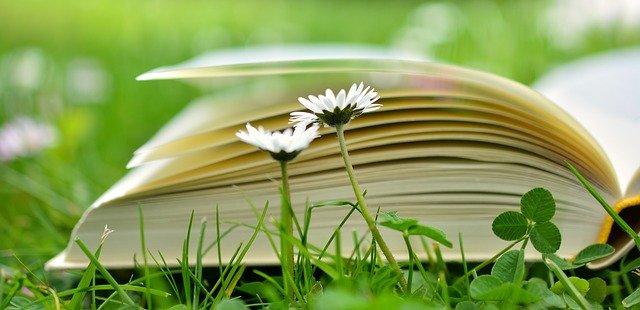
保育士を目指している人や、保育業界に携わっている方にとっては、このことについて自身の中で考えたり周りと話したりする機会があったのではないでしょうか。
実際に、現在保育士として就業していない方にとっては、潜在保育士が多く待機児童門が解決しないことについてメディア等で取り上げられる度に、「そうそう」「いや、そういうことではない」などと、自身の状況を踏まえて振り返ることもあったでしょう。
潜在保育士の人数は、約80万人。120万人いる保育士資格登録者のうち、保育士として就業している人は40万人と言われており、3分の2は保育士として就業していないのが潜在保育士の現状です。
「どうして、保育士として就業していないのか。」
「潜在保育士から保育士として就業するために、国や自治体による支援制度はあるのか。」
「そもそも、潜在保育士が多いのはどうしてだろうか。」
本記事では、潜在保育士に関する疑問を解消していきます。
保育士の資格をもっていながら保育士として就業していない方が、これから保育士として就業するために、どのように就職活動に取り組んでいくといいのか改めて考える機会にしましょう。
潜在保育士でも実情はさまざま
潜在保育士とは、保育士資格をもちながらも就業していない方のことです。これまで、保育施設等での就業経験がある方もない方もどちらも該当します。また、これから保育士として就業したいか、という就業の意思も関係ありません。
保育学校の卒業後、資格は取得したけど保育業界でない会社へ就職している方も、保育園で働いていたけど出産を機に退職した方も、同じ「潜在保育士」です。
また、保育士として就職するために求職活動を行っている方も、今後保育士として就業する予定がない方も、同じ「潜在保育士」の括りに分けられます。
保育士として就業したくてもできない潜在保育士も多い
厚生労働省の「潜在保育士ガイドブック」によると、潜在保育士が保育士として就業しない・できない理由は主に2点でした。
1点目は、結婚・出産。土曜出勤や早番・遅番といった変動制の勤務時間、業務内容の多さなどにより、ワーク・ライフ・バランスをとるのが難しいという理由です。
この調査では、潜在保育士の75%が「配偶者あり」で、さらに69%が「子どもあり」だったため、このような意見が多く見られました。特に、未就学児の子どもがいるほど潜在保育士の割合が高く、「今、自分の子どもを預けても保育士として仕事したいのか」、子どもが好きだからこそ思い悩む方が多いようです。
2点目は、待遇面。業務内容と給与のギャップを感じ、退職してしまう方も少なくありません。給与面以外でも、拘束時間の長さや業務量の多さを理由に、別の職業へ転職する方もいます。

保育士として就業したい意思があっても、条件に合う求人が無いことを理由に保育士として就業できない方も多いのが実情です。
人材不足が指摘され、保育士確保プランなど国や自治体による支援制度がスタートし、有効求人倍率も全体平均と比較して高い中で、「就業したくてもできない潜在保育士」が多いのは、保育士の9割が女性という職業柄が少なからず影響しています。
この「潜在保育士ガイドブック」の調査結果を踏まえ、2015年以降、次のような取り組みが始まりました。
潜在保育士向けの支援制度
◆潜在保育士就職準備金
潜在保育士が新たに保育士となった場合に、保育園等の就職に必要な資金を貸し付けられる制度です。継続して2年以上保育所等で勤務し続けた場合、貸付の返還が免除されます。
貸し付けられるのは1回限り、40万円以内です。

〇対象者
・資格を取得してから、保育士として従事するまで1年以上の方
・事業主催者の管轄内の保育所等に、新たに従事する方
週20時間以上勤務していれば、パート勤務者でも対象となります。
自分の希望を満たす働き方や待遇がある求人に応募するために、他の都道府県に引っ越すことを視野に入れられるようになる方もいるのではないでしょうか。
今住んでいる都道府県内にとどまらず、この制度を活用することを前提として、広範囲の求人情報を収集するのもいいでしょう。
◆未就学児をもつ保育士に対する保育料の一部貸し付け事業
保育士の子ども(未就学児)にかかる保育料を無利子で貸付けられる制度です。継続して2年以上保育所等で勤務し続けた場合、貸付の返還が免除されます。
〇対象者
・未成年の子どもをもつ保育士
・事業主催者の管轄内の保育所等に従事している方
週20時間以上勤務していれば、パート勤務者でも対象となります。
貸付金額は保育料の半額(上限27,000円)です。
自治体によっては、貸付金額の上限が倍額の54,000円のところや公立保育園は対象外としているところもあります。また、既に保育所等で勤務していて産休・育休から復帰する方も対象にしているところもあるので(和歌山県など)、潜在保育士でなくても活用できる制度です。
◆未就学児をもつ保育士の子どもの預かり支援事業利用料金の一部貸付
ファミリー・サポート・センター事業やベビーシッター派遣事業等の預かり支援事業の利用料金の一部を貸し付ける制度です。継続して2年以上保育所等で勤務し続けた場合、貸付の返還が免除されます。貸付金額は利用料金の半額(上限は、年額123,000円)で、貸付期間は2年間までです。
〇対象者
・未就学児の子どもをもつ保育士
・事業主催者の管轄内の保育所等に従事している方
特段、勤務時間上で制限はありません。
子育てをしながら保育士として働く時に気にかかることの一つに、「早番や遅番勤務の時に、子どもを預けている保育園の開園時間内に送迎できない」を挙げる方は多いです。
例えば、早番で7時までに出勤しなければならない時に、大半の保育園は開園時間が7時なので、自分の子どもを預けられずに早番・遅番勤務ができないといったことがあります。家族の協力を得られない方にとっては、子どもが未就学児の間は正社員で保育士として働くことを諦めざるを得ない方も少なくありませんでした。
けれどもこの制度を活用することによって、このように保育所等の勤務時間によって、自身の子どもの預け先に困ったり働きづらさを抱えたりする方が減ることが期待されています。
それぞれの支援制度は、各自治体によって管轄されています。都道府県主体で実施しているところもあれば、指定都市は市が主体となっているところも。対象者や貸付金額に違いがあるので、制度の詳細は各都道府県や社会福祉協議会のホームページで必ず確認するようにしましょう。
保育実践の研修に参加する
保育所等を退職してからブランクが長い方や資格をもっているけれども保育所等で旗就業した経験がない方を対象として、各都道府県に設置されている保育士・保育所就職支援センターを中心に研修が実施されています。
具体的な内容は自治体によって差があるものの、「保育所保育指針の改定について」や「乳幼児の救命救急」、「感染予防・アレルギー対応」など豊富に開催されているところも多いです。
保育士として就業することに独学だけでは不安がある方は、研修を受講することをおすすめします。

潜在保育士の力が必要とされている
就職準備金や保育士の未就学児にかかる保育料の貸付といった一時的な補助金だけでなく、保育士全体の給与のベースアップや住宅手当等の拡充、キャリアアップ研修制度などにより、保育士として長く働くことができるよう、ここ数年で保育士をとりまく環境が多角的に良くなってきています。
実際に、給与面だけで言うと、保育士の給与は5%引き上げられており、東京都に限っては、この5年で44,000円相当の処遇改善が行われています。その他の自治体でも、2015年に策定された「保育士確保プラン」に則り、独自の制度を実施し、人材確保に努めています。
待遇が少しずつ見直されてきていて、人材不足故にたくさんの求人から自分の希望に添ったものを比較的見つけやすい今、少しでも保育士として就業することを考えている方にとっていい時期と言えるのかもしれません。
一人で就職活動を行うより、保育士専門エージェントのサポートが受けられる人材紹介会社を利用するなどして、たくさんの情報やアドバイスが受けながら、保育士資格を活かし活躍するための一歩を踏み出していきましょう。
 閲覧履歴
閲覧履歴
 最近見たお仕事
最近見たお仕事