みんな知ってる?保育業界の用語集★
保育業界で働いていると、子どもの発達に関する言葉がたくさん出てきます。
育児を経験していれば何となくわかる言葉でも、新卒採用などで育児経験がないと「どういう意味?」と戸惑う方も多いです。
そこで今回は保育業界でよく使われる用語を、
- 発達
- 保育・活動
- 食事
- その他
の4つにわけて説明していきます。
知っておくと、カリキュラムなどを書く際に役立つので、しっかり覚えておきましょう。

発達に関する保育用語
まずは子どもの発達に関わる保育用語から確認していきましょう。
愛着
愛着とは子どもが特定の他者に対して抱く、情緒的な結びつきのことです。
保育業界では「愛着形成」という言葉がよく使われます。
愛着形成は子どもの心の発達に欠かせないものなので、子どもとの愛着形成をしっかり築けるようにすることが大切です。
〇語文
0~2歳児クラスでよく使われる言葉です。
「ワンワン」「ブーブ」などの単語を1語文、「ワンワン いた」「ブーブ きた」のように後ろに言葉が続くと2語文というように使われます。
1語文がでてきたら、保育者が「本当だ。ワンワンいたね」など子どもの気持ちを代弁しながら2語文に繋がるような声掛けをすることが大切です。
基本的生活習慣
「睡眠・食事・排泄・清潔・衣類の着脱」の5つのことを基本的生活習慣と呼びます。
基本的生活習慣は生活の基盤となるもので、心身ともに健康に育つために欠かせないものなので、身に付くように援助していく必要があります。
発達障害
様々な要因によって、発達に支障があることです。
発達障害には、ADHD、アスペルガー症候群、自閉症など様々な種類があり、症状も異なるため、深い知識が必要です。
子どもの様子を保護者としっかりコミュニケーションをとって確認しながら、必要によっては病院や療育機関を勧めることも必要になります。
退行現象
いわゆる「赤ちゃん返り」のことです。
これまで出来ていたことが出来なくなり、前の段階に逆戻りすることで、これまでスプーンを使って食事していたのに手づかみ食べになったり、トイレで排泄できていたのにおもらしをするようになるなどが挙げられます。
進級・親の妊娠や出産・引っ越し等の子どもを取り巻く環境の変化から起こることが多いです。
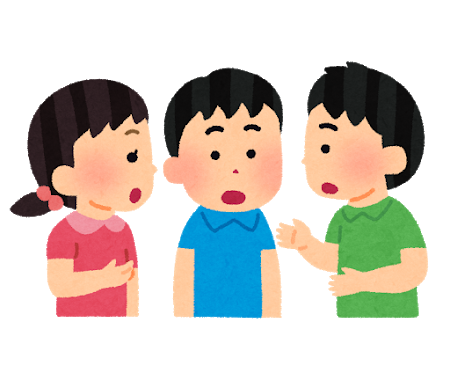
保育・活動に関する保育用語
次は日々の保育や活動に関わる保育用語についてです。
一斉保育
クラス全員で同じ活動をすることです。
設定保育と呼ばれることもあり、決まったものを作る製作や、椅子取りゲームなどのルールのある遊びなどが一斉保育に当たります。
反対に子どもの興味や関心を尊重して、やりたいことをやらせてあげる保育を自由保育と言います。
異年齢児保育
0歳児クラス、4歳児クラスのようにクラス単位での活動ではなく、0~2歳児、3~5歳児といったように、様々な年齢の子どもで活動することで、縦割り保育と呼ばれることもあります。
小さい子は大きい子の真似をしたり、大きい子は小さい子に優しくしたりと、それぞれの年齢による育ち合いが期待できます。
園外保育
遠足のような戸外で行う保育のことです。
園によって、日々の散歩は園内保育と呼ぶところもあれば、散歩のことも園外保育と呼ぶところがあったりと、園外保育の設定は園によって異なります。
コーナー保育
いくつかの遊びを設定して、子どもが自分で遊びを選んで活動する保育のことです。
「粘土コーナー」「お絵描きコーナー」のように考えると、イメージがしやすいかと思います。
子ども1人1人やりたい遊びは違うので、コーナーを設定することで、自分の好きな遊びで遊びこめるというメリットがあります。
リトミック
音楽に触れて音楽能力を伸ばしながら、感覚的・知的・身体的な発達を促す遊びのことです。
音楽に合わせて手遊びや体操など、体を動かして遊び、体の動かし方を学んでいくことから始め、発達に合わせて難易度をあげ、反射神経やリズム感等を養うこともできます。

食事に関する保育用語
続いて食事に関わる保育用語を紹介していきます。
アレルギー除去食
アレルギーのある子の食事から、アレルゲンを取り除いた食事のことです。
例えば給食の主食が食パンの日に、小麦アレルギーの子に米粉パンを提供する、といったものがアレルギー除去食になります。
アレルギーはアナフィラキシーショック等を引き起こす場合もあるので、給食室の職員は勿論、保育士もしっかり確認することが大切です。
遊び食べ
離乳食後期~1歳前半頃におこりやすく、食べ物を下に落とす・手でぐしゃぐしゃにする・スプーンで机や食器を叩くなど、食事中に遊びながら食事をすることです。
始めのうちは食材に興味を持っている証拠なので、見守りながら、少しずつ遊び食べをしないよう声掛けをしていくことが大切です。
三角食べ
バランス食べとも呼ばれますが、一定のものだけを食べ進めるのではなく、食事全体をバランスよく食べ進めることです。
子どもは自分の好きなものばかり食べたり、ご飯を全部食べてからスープを全部飲み、それからおかずを食べるというような食べ方をする子が多いです。
そのため、全体的に同じくらいのペースでバランスよく食べられるように声掛けをして、三角食べができるよう援助していくことが大切です。
食育
食に対する正しい知識や、正しい食習慣を身に付けるために重要なものです。
日々の食事の中での食事のマナーや、好き嫌いせずバランスよく食事をすることは勿論、実際に野菜を育てたり調理したりして、食べ物を大切にする心を育んだりすることも食育に含まれます。
偏食
好き嫌いのことで、特定のものを嫌がって食べない・特定のものがないと食事が進まないといった状態のことです。
白米しか食べない・緑色のものは食べないなどは、比較的よく見られます。
あまりに偏食がひどい場合には、発達障害が理由である可能性も考慮することが必要です。
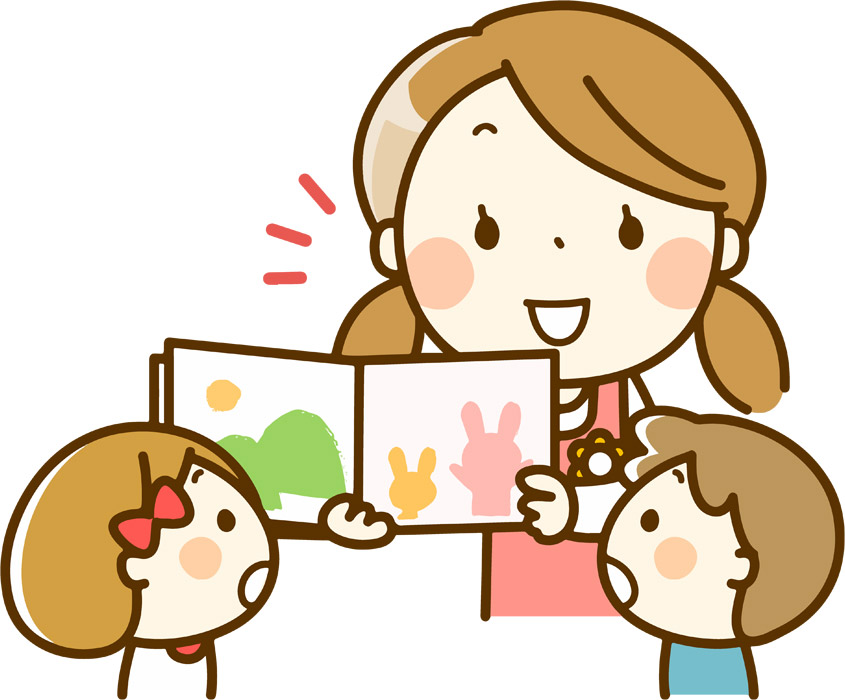
その他の保育用語
最後にその他の保育用語について紹介します。
環境構成
保育を行うのに必要な環境づくりのことです。
環境づくりといっても、物理的なものだけではなく、人的・心理的なものも環境構成に含まれます。
環境構成を考えて日々の保育をすることが大切です。
児童表
入園している子どもと、その保護者の基本的な情報が書かれた書類のことです。
児童表は子どもの成長を記録する大切な書類のため、取り扱いには細心の注意が必要です。
慣らし保育
4月に新入園児を対象に行われる、短時間保育のことです。
段階的に保育時間を延ばしていき、子どもが無理なく園生活に慣れていけるように行うもので、2週間前後行われるのが一般的です。
保護者としっかりコミュニケーションをとりながら進めていくことが大切になります。
月案指導計画
「月案」と呼ばれるもので、ねらい・環境構成・遊び・生活・家庭との連携など、日々の生活を1か月単位で計画するものです。
年間カリキュラムを元に月案を作成し、月案をもとに週案や日案を作成していきます。
このように計画を立てて保育を行うことで、子ども達をどのように保育していくのかを明確にすることができるため、とても大切な書類です。
個別計画
3歳未満の子どもは、月齢などによって発達の差が大きいため、月案とは別に個人の発達に合わせて個別的な計画を立てます。
これにより、子ども1人1人の発達に合った援助・保育をすることができます。
今回紹介した用語は、どれも保育園ではよく使われる用語です。
覚えておくことで日々の保育は勿論、書類作成にも役立つので、しっかり抑えておきましょう。
 閲覧履歴
閲覧履歴
 最近見たお仕事
最近見たお仕事