保育士辞めたい・・・5月病の乗り越え方!
新年度が始まって1ヶ月が過ぎ、疲れが出てくるころではないでしょうか。
ドタバタと忙しい中、少しずつ子ども達が新しいクラスに慣れてきて、様子を見ながら保育を進めていた4月が終わり、ゴールデンウィークという長期休みをはさむと「仕事行たくない…保育士辞めたい…」と思う方も多いです。
そこで今回は、保育士の5月病の特徴や、5月病の乗り越え方について紹介していきます。
ぜひ参考にして、5月病を乗り越えましょう。

保育士の5月病の特徴
通常では、5月病は新入社員に起こりやすいものです。
新しい環境にとにかく必死で、疲れが溜まったところでの長期休み。
「このまま仕事辞めたい…」と思ってしまうのも無理はないですよね。
しかし、保育士は新卒保育士に限らず、誰にでも起こりやすいのです。
大きな理由の1つとして、毎年4月になると1からやり直しをしなければいけないということが挙げられます。
保育園では担任が持ちあがりではない場合も多いです。
そのため、例えば4歳の担任から0歳の担任になると、子どもへの援助内容が増えたり、乳児クラスでは複数担任の園も多いので、他の保育士との連携をとらなければいけません。
逆に幼児クラスでは、子どもの出来ることは多いものの、仕事を1人でこなさなければならなかったり、子どもの動きが大きくなる分、怪我のないよう注意する必要があるので、どちらも肉体的・精神的に負担になります。
そのため、新人保育士だけでなく、ベテラン保育士も5月病になる可能性があります。
ベテラン保育士が5月病になったとしても自分を責めず、保育士は誰でも5月病になりやすいということを覚えておくと、気が楽になりますよ。
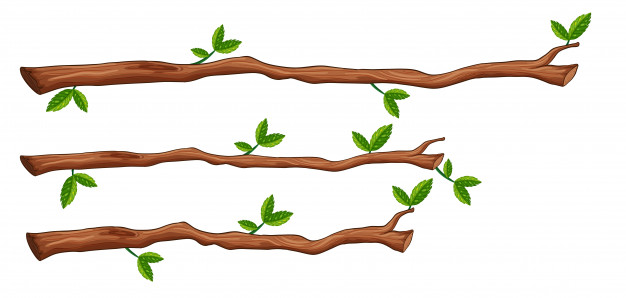
保育士ならではの5月病の悩み
なぜ「保育士辞めたい」と思ってしまうのか、保育士ならではの5月病の悩みについて、4つ紹介していきます。
保育士間の連携がうまくとれない
新人保育士と、ベテラン保育士の人間関係も勿論ですが、これまで同僚として仲良くやっていても、同じクラスになると仕事が上手くまわらないというのは、比較的よくある話です。
うまく仕事がまわらないと、休憩がしっかり取れなかったり残業をしたりと、疲れは溜まっていく一方です。
しっかりと保育の進め方について、詳しく話し合う必要があります。
保護者との関わり
保護者との関わりは、信頼関係を築いていくうえで重要なものですが、上手く関われずに悩んでしまい、「自分は向いていないのではないか」と悩んでしまうことがあります。
毎年新しい保護者が入ってくるので、4月になると、1から保護者との信頼関係を築いていかなければならないというのも、保育士の5月病ならではです。
保護者との関わりは、長期的に築いていくことが大切なので、焦らずしっかりコミュニケーションを取っていくことを心掛けるようにしましょう。
待遇の悪さ
保育士は子どもの命を預かる、責任感のある仕事です。
それに加えて、子どもの成長を促すような活動を考えたり、月案などの書類、製作物の準備など、仕事量が多く、残業や仕事の持ち帰りもあり、仕事時間も長いです。
しかし、他の仕事に比べると給料はかなり低いです。
この待遇の悪さから、保育士として続けていくのが辛いと思ってしまう人が多いです。
以前に比べると保育士の給料も少しあがり、自治体で独自の支援をしているところもあります。
給料が全てではありませんが、生活していくうえでも、自身のモチベーションを保つためにも大切なものになるので、あまりに辛いようであれば転職を考えるのも1つの手です。
思い通りに保育が出来ないもどかしさ
保育士であれば「子どもと笑顔で、元気に楽しく過ごしたい」という想いがあるかと思います。
しかし実際は、子どもが言うことを聞かなかったり、喧嘩をしたり、予定通り保育が進まなくてつい厳しい言葉がけをしてしまうこともあります。
その時に「もっと優しく声をかけてあげれば良かった」「子ども達が楽しめるようにもっと工夫すればよかった」と自分を責めてしまい、それが心労として溜まってしまうことがあります。
自分が思い描いていた理想像と、現実のギャップに打ちのめされてしまうというのは、新卒保育士に多いです。

保育士の5月病の乗り越え方
では実際にどのように5月病を乗り越えればいいのか、おすすめの方法を4つ紹介していきます。
誰かに相談する
保育の悩みで、解決したいと思っているのなら保育士仲間に、単純に話すことでスッキリするのなら親や友人などに話を聞いてもらうのがいいでしょう。
心にためておくと、どんどんストレスが大きくなってしまうので、定期的に気持ちを吐き出すことがおすすめです。
具体的な解決にならなかったとしても、気持ちを吐き出して、話を聞いてもらい「大変だね」と共感してもらうだけでも、気持ちがスッと楽になりますよ。
リフレッシュする
特に新卒保育士は、仕事終わりや休みの日など、常に仕事のことを考えている人が多いです。
オン・オフをしっかりつけて、自分の時間を大切にすることも必要です。
どこかに出かけたり、運動したりするのもいいですし、仕事終わりで時間がとれないときは、ゆっくりお風呂に浸かって好きな音楽を聞く・好きな食べ物を食べる・翌日に響かない程度にお酒を飲むなどもおすすめです。
仕事終わりや休日は自分の時間を楽しむことで、仕事を頑張ろうというモチベーションアップに繋がります。
現状について整理する
なぜ自分は保育士を辞めたい、仕事に行きたくないと思っているのかについて考えてみましょう。
単純に休みが楽しかった・また仕事に行くのが面倒くさいという場合は、行ってしまえば楽しんで仕事ができることも多いです。
人間関係や待遇の悪さから苦しいのであれば、転職を考えて他の園の求人を見てみたり、漠然と仕事へ行くことに不安や恐怖心を感じるようであれば病院を受診したりと、自分が今やるべきことが見えてきます。
自分がどうしてそう思うのか、解決するにはどうしたらいいのかについて、自分で考えてみるというのは、自分とじっくり向き合ういい機会にもなるのでおすすめです。
職場での楽しみを見つける
例えば、書類は苦手だけど子どもと関わるのは楽しいと思っているのなら、まずは子どもと遊ぶことだけを考えましょう。
5月病になると、辛いことばかりに目がいって、楽しいことが見えなくなってしまいがちです。
そのため、まずは自分は何を楽しいと思っているのかについて改めて考えることで、仕事へ行くということへのハードルが下がります。
子どもと遊ぶといった仕事の内容に限らず、同期と話すのが楽しいといった理由でも大丈夫ですよ。

今回は保育士ならではの5月病の悩みや、その乗り越え方について紹介しました。
5月病は夏ごろには症状がなくなっていることも多く、乗り越えた後は保育の仕事の楽しさを感じられるはずです。
「保育士辞めたい」と思ったら、ぜひ今回紹介したことを試してほしいと思います。
しかし、5月病は無理をするとうつ病になってしまう可能性もあります。
本当に辛いと思ったら、退職や転職、病院を受診するということを検討することも必要です。
5月病は多くの人が経験するものなので、決して自分を責めたりせず、ストレスをためすぎないようにしてください。
 閲覧履歴
閲覧履歴
 最近見たお仕事
最近見たお仕事