お泊り保育ってどんなことするの?注意点や盛り上がるイベントをご紹介
幼稚園・保育園の年長クラスで行われることの多いお泊り保育。
子ども達が家族と離れて、友達や先生と1日過ごすので不安半分、楽しみ半分でドキドキしている子どもが多い一大イベントです。
子ども達の不安を取り除きながら、安心して楽しく過ごせるようにするには、子ども達が思いきり楽しめるイベントを考えたり、怪我などがないよう注意すべき点を再確認したりすることが大切です。
今回はお泊り保育とは何かについて説明しながら、注意点や子ども達が楽しく盛り上がることのできるイベントまで、詳しく紹介してきます。

お泊り保育とは
お泊り保育は家族と離れて保育園や幼稚園の友達・先生と一緒に過ごすイベントです。
多くの園が7~8月の夏の時期に1泊2日で設定して行っています。
卒園前の思い出作りも兼ねて5歳児クラスで行う園が多いですが、中には4歳児クラスから行っている園もあります。
内容については園によって大きく異なり、園で宿泊する場合は普段の活動に少し特別感を取り入れた活動をしながら、園で夕飯やお風呂を済ませて就寝したり、日帰りで水族館や動物園に遠足に行き、帰園して宿泊したりする場合が多いです。
園外で宿泊する場合には、宿泊施設やログハウスを利用して大自然の中で過ごすというような非日常を味わえるような活動を取り入れる園が多い傾向にあります。
お泊り保育の主なねらいは
- 家族と離れて外泊し、自立心を育む
- 他児と協力して過ごし、協調性を身に付けていく
- 身の回りのことを自分で行う習慣を付けていく
などが挙げられます。
家族と離れて外泊をするというのは、私たちの想像以上に子どもにとっては不安の大きい事ですが、乗り越えることで自信がつき、自立心を育てることに繋がります。
また、特に保育園の子どもの多くは両親が働いていて時間が限られていることもあり、食事の準備や身体を洗う・拭くなどは親が行っている家庭も多いです。
他児と協力しながら食事を作ったり、身の回りのことを自分で行ったりすることで、協調性や自分で行うという習慣をつけていくことに繋がります。
お泊り保育は楽しいだけでなく、子ども達が小学生になるに向けて自立心や協調性を身に付けるためにとても大切な行事なのです。

お泊り保育で盛り上がるイベント5選
お泊り保育では時間もたくさんあるので、普段の活動にプラスしていつもは出来ない体験をさせてあげることで、お泊り保育ならではの特別感を味わうことができます。
園内宿泊時に、お泊り保育だからこそ盛り上がるイベントを5つ紹介していきます。
1.スタンプラリー
普段は他の保育室で過ごしている園児もお泊り保育の日はお休みでいないので、園全体を使った活動は特別感があります。
各コーナーでボーリングや射的のようなゲームを用意して、クリアできたらスタンプを押し、全て集まったら景品が貰えるようにすると楽しく参加することが出来ます。
どこでゲームを行っているのを事前に伝えず地図を作って渡すことで、他児と協力する・地図の概念を理解するということも促せます。
2.宝探し
こちらも園内全体を使った宝探しにすることで特別感を味わうことが出来ます。
4・5歳児はなぞなぞやクイズへの興味も出てくる年齢になるので、グループ分けをしてそれぞれのグループに隠し場所を示したクイズを出して探すようにすることで、他児と協力しながら自分たちで考えて行動する力を養うことが出来ます。
3.買い出し・料理
普段は給食室の先生や保護者が作ってくれる食事を、子ども達で作ることで、協調性は勿論のこと、食事を作ることの大変さや、食材への感謝など食育に繋がります。
保育者が用意した食材を使って料理するだけでなく、例えばカレーの場合、カレーの具材は何にするかを決めるところから始めて、必要な食材を買いに行くことでお金のやり取りを経験することが出来ます。
料理は夜だけという園も多いですが、朝は保育士が具材をあらかじめ用意しておいて、ホットケーキやサンドイッチなどに好きな具材を乗せるというのも楽しいですよ。
4.花火・キャンプファイヤー
夏ならではのイベントを取り入れることで季節を感じることが出来ます。
お友達と一緒に花火やキャンプファイヤーをするというのは子ども達にとってとても特別感のあるイベントです。
火を使う活動なので事前に子ども達に注意点や約束事を伝えておくことが大切です。
花火の場合、手持ち花火が終わった後に保育士が打ち上げ花火をあげると、子ども達はとても喜びますよ。
5.上映会
夜遅くなってくると、寂しくなったり不安になったりする子もいます。
そこで、1日の様子を撮影したものを上映会のようにして子ども達と見ることで、楽しかった気持ちがよみがえってきます。
短時間で動画を編集するのは難しいですが、ありのままの写真や動画をスライドショー方式で上映するだけでも子ども達は充分楽しむことが出来ます。
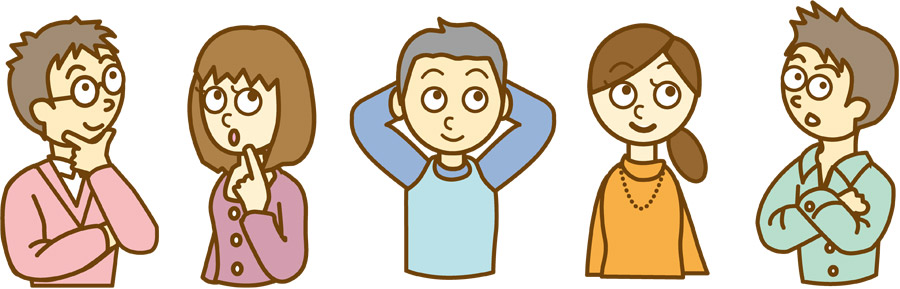
お泊り保育での注意点
お泊り保育は楽しいことばかりではありません。
普段は最長でも12時間程度の保育時間ですが、お泊り保育では24時間以上子どもを預かり、普段の保育では出来ないような活動をするため、普段の保育以上に注意が必要です。
そこで、お泊り保育で注意すべき点を3つ紹介します。
1.事前準備
保育を進める上で計画通りにいかないこともありますが、まずはどのように過ごすのかを決め、そこから想定される子どもの様子などをしっかりと想像し、準備しておくことが大切です。
例えばお風呂であれば、まだ自分で洗えない子もいるため少人数ずつにする、保育士が湯船と洗い場に1人ずつ配置するなど流れを決めた後に具体的に決めておくことが大切です。
また、基本的にお泊り保育は担任が主体となって流れを決めますが、当日は他クラスの保育士とも連携して過ごすため、しっかりと全職員で1日の流れを把握しておく必要があります。
また、持病や不安定になりやすいなど配慮が必要な児はあらかじめ伝えておき、全職員が把握・対応できるようにしておくことが大切です。
2.子どもや保護者の心の準備
子どもはお友達と1日一緒に遊べることで頭がいっぱいで、いざ夜になると寂しくなったり不安になったりする子もいます。
そのため、事前に夜もお友達や先生と一緒に過ごすということ、家族が迎えに来るのは何日の何時頃なのかなどをしっかり説明しておく必要があります。
また、保護者も家族以外の人に子どもを1日以上預けるという経験がある人はそう多くありません。
子ども以上に不安を感じる保護者もいるため、当日の流れや想像される子どもの様子を伝えておき、保護者も安心して送り出せるような心の準備をすることも大切です。
また、何かあった時の連絡先(何時までは会社で何時からは携帯に連絡など)を確認し場合によって夜遅くに連絡する可能性もあることなどもしっかりと伝えておきましょう。
3.子どもの体調管理
その日の体調は勿論ですが、中には持病などで朝晩に薬を服用している子どももいます。
必ず事前に薬の服用の有無などを確認し、必要に応じて投薬して子どもが健康に参加できるようにする必要があります。
また、夜になって不安や寂しさなどから不安定になる子どもには傍に寄り添ったりあまりに落ち着かないようであれば保護者に連絡をしたりするなどの対応が必要です。
お泊り保育は子ども達にとって特別で楽しい行事です。
子ども達が安全に楽しく過ごせるよう、保育士がしっかりと計画・準備・援助をして、子ども達の記憶に残るお泊り保育にしてあげてくださいね。

 閲覧履歴
閲覧履歴
 最近見たお仕事
最近見たお仕事