園児同士のケンカ、保育士としての対応について
園生活で避けて通れないのが、園児同士のケンカです。
ケンカと一言で言っても、ちょっとした言い争いから、怪我に繋がってしまうようなものまで様々です。
今回は乳児・幼児それぞれに多いケンカの原因や事例と共に、ケンカが起きたときの対応方法について、詳しく紹介していきます。

乳児で多いケンカの原因
乳児で起こるケンカの原因には
- 玩具の取り合い
- 自分の思い通りにならない
- 他児との関わり方がわかっていない
などが挙げられます。
乳児のケンカの事例と対応方法
1.玩具の取り合い
0~1歳児前半では、他児が使っていた玩具をとってしまって、取られた他児が怒ったり、取り返そうとしたりすることからケンカへ発展するというのは、日常的に見られるケンカの1つです。
また、1歳児後半~2歳児になると、他児との関わりが何となく理解できるようになってきて「貸して」と言葉で伝えられるようになってきますが、貸して=貸してくれるという考えの子どもも多く、「貸してと言ったのに貸してもらえない」ことがケンカの原因となることも多いです。
対応方法
どのケンカにも共通して言えることですが、まずは子どもの気持ちに寄り添います。
「使いたかったの?」、「貸してもらえなくて悲しかったの?」と、子どもの気持ちに寄り添って代弁します。
そのあとで、他児の玩具を勝手に取ってしまった場合には他児が使っていたこと・使いたい時には「貸して」と聞いてみることなどを、根気強くケンカのたびに伝えていきます。
また、貸してと言ったのに貸してもらえなかった場合には、他児の言い分も聞いてあげることが大切です。
「まだ使いたかったの?」「今遊んでいるの?」と、貸したくない理由を確認し、「10数えたら交換」「長い針が2になったら交代」「これを使って一緒に遊ぶのはどう?」など、
お互いが納得して遊べるような提案をします。
始めから保育士が決めるのでなく、あくまで保育士は提案をする程度にして、園児同士で納得して決められるように促すことが大切です。
2.自分の思い通りにならない
仲良く同じ玩具で遊んでいたと思ったら、次の瞬間にはケンカをしているというのも日常的に目にするケンカの1つです。
例えば一緒にブロックを積み重ねて遊んでいた際に、「次は青を重ねようと思っていたのにもう1人が赤のブロックを重ねた」など、自分が思っていたものと違う時にケンカに発展することがあります。
対応方法
そういった時には、どうしたかったのかを訪ねて子どもの気持ちを確認します。
また、相手の子にも「青のブロックが良かったんだって」と、もう1人の気持ちを伝えてあげます。
そのうえで「じゃあ次は何色にする?」「次は○○ちゃんが色きめようか」と、言葉で伝えられるように促したり、順番で遊ぶことを覚えられるようにしたり援助を行っていきます。
3.他児との関わり方がわかっていない
年下の子を可愛がっているつもりで叩いたり、戦いごっこをしているつもりでお友達を蹴ったり、お友達が積み上げた積み木を壊して、積み木の崩れる様子を楽しんだりと、悪気はなくともお友達との関わりがわかっていないが故にケンカが起こることが乳児の場合は多くあります。
対応方法
その都度正しい関わり方を伝えたり、絵本を通して他児との関わり方や相手の気持ちを考えられるように促したりしていくことが大切です。
「それだと痛いから、いいこいいこしてあげて?」「本当に叩かれたらどうかな?痛くないかな?」「頑張って作ったものを壊されたら悲しい気持ちだよ」と、相手の気持ちを理解できるように促していきます。
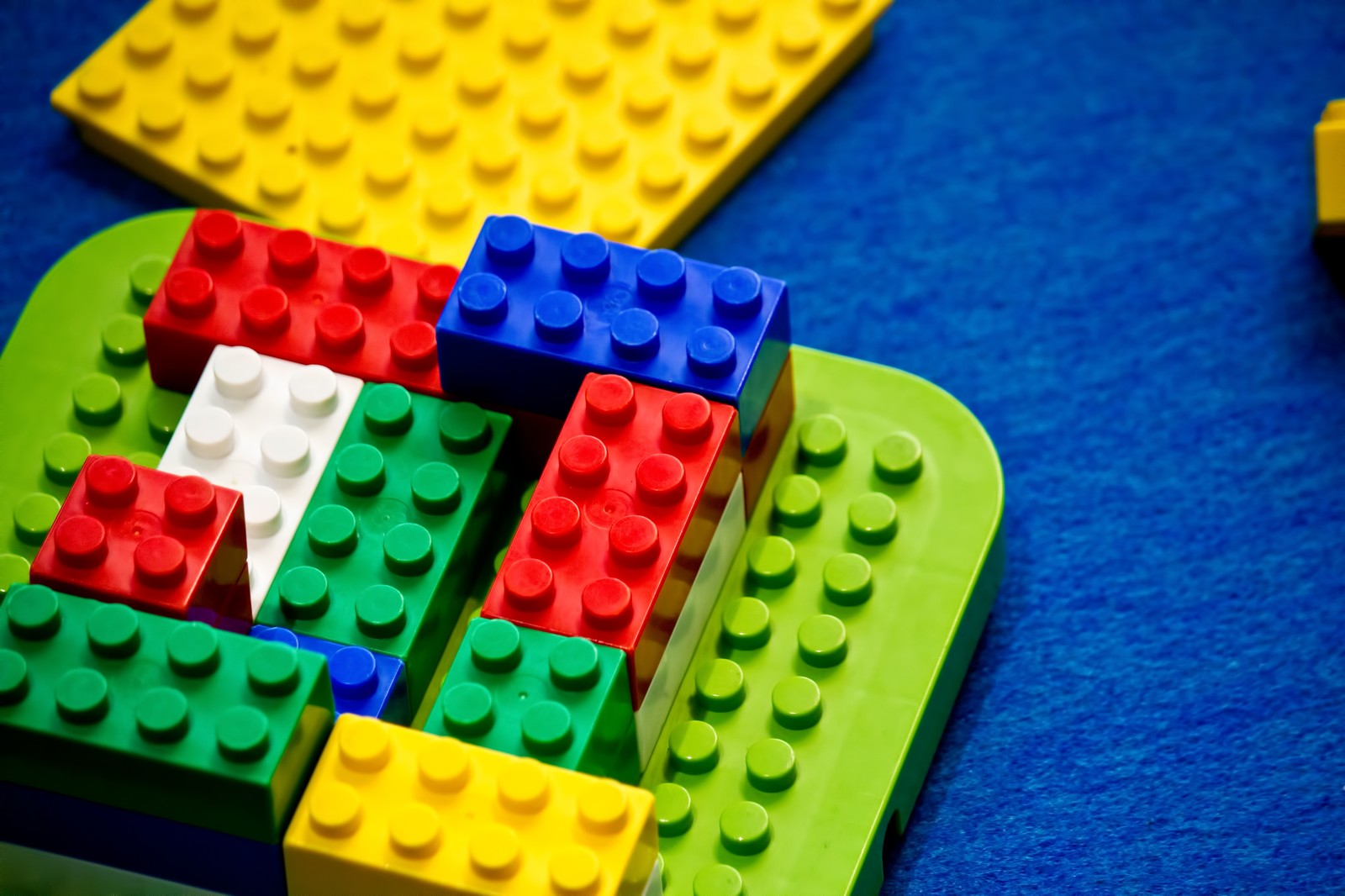
ケンカという経験から得られるものもあるため、すぐにとめる必要はありませんが、乳児の場合にはケンカの際に手や口が出てしまうことが多いため、些細なトラブルでもすぐにとめられる位置から見守り、怪我を防ぐことが大切です。
実際に手や口が出てしまった時にはいけないことだと伝えながら、身振りや言葉で気持ちを伝えられるように援助することが大切です。
また、怪我をしてしまった際には保護者に謝罪をしながらその時の状況を説明し、怪我の処置やその後の子どもの様子についても丁寧に説明をすることで、保護者トラブルを避けることに繋がります。
保護者対応の例
「玩具の取り合いをしている時にお友達に噛まれてしまいました。未然に防ぐことが出来ず申し訳ありません。すぐに流水で冷やして、今はこのような状態です。
その後噛まれたところを痛がったりする様子はなく、噛んでしまったお友達とも仲良く遊ぶことが出来ていますが、お家で痛がる様子などあれば明日の登園時に伝えてもらえればと思います。本当に申し訳ありませんでした。」
幼児で多いケンカの原因
幼児で起こるケンカの原因には
- 双方の意見の違い
- 競争心
- ルールや約束を守らない
などが挙げられます。
幼児のケンカの事例と対応方法
1.双方の意見の違い
お互いにやりたいものが違ったり、同じ遊びでもやりたい流れが違ったり…遊びに工夫が出てくる幼児だからこそのケンカがでてきます。
例えば、ままごとをする際に「誰が何役をするのか」でケンカになることがあります。
誰かが「私がお母さん役やりたい」と言えば「私もお母さんやりたい」「お母さん役は○○ちゃんがいい」など、様々な意見が出て、その話しがうまくまとまらずにケンカへと発展していきます。
対応方法
子どものケンカの原因が何かを把握し、見守ります。
子どもから助けを求められたり、ケンカがあまりに熱くなっていくようであれば保育士が仲介に入ります。
その際には、1人1人の意見を聞き、「みんなそういう風に思っているんだね、じゃあどうしたらいいかな?」と、その場の状況を整理してあげて、子ども達での解決ができるように促すことが大切です。
2.競争心
幼児になると「1番になりたい」という気持ちが強くなってきます。
かけっこやゲームなどでは競争心があることは大切ですが、並ぶときに1番前がいい・「その玩具で遊ぶのは俺が1番がよかった」など、大人から見ると些細なことでも1番にこだわることがあります。
1番になりたいがゆえに他児を抜かしたり押したりしてケンカに発展することもしばしばです。
対応方法
「1番になりたい」という気持ちは受け止めながらも、「ずる(押したり抜かしたり)して1番になってもかっこよくないよ」と、事実を伝えます。
「抜かされたらお友達だって嫌な気持ちになる」「ずるして1番になるよりも順番を守って並べる方がかっこいい」と、相手の気持ちも伝えていきます。
また、「1番じゃなかったけど、かっこよく丁寧にお支度してたの見てたよ」と、1番に慣れなかった過程を褒めてあげることもおすすめです。
3.ルールや約束を守らない
子ども同士で話し合って色々なことを決められる幼児だからこそ「長い針が2になったら変わる」「タッチされたら負け」など、子ども同士で決めたルールや約束を守れずにケンカに発展することが多いです。
対応方法
日々の保育の中で絵本なども活用しながら「ルールや約束を守ることの大切さ」について子ども達に伝えることが大切です。
どんな約束・ルールだったのかを保育士が確認し、今の状況を整理します。
そのうえで、なぜ約束やルールを守れなかったのか(「もっと遊びたくなっちゃった?」など)を確認し、どうしたらいいかを子ども達に問いかけます。
あくまで保育士は状況を確認する程度にとどめ、子ども達で解決できるように導くことが大切です。
幼児の場合は手が出るよりも、言葉でケンカをすることが多いですが、話しが平行線になり解決が難しくなってしまうこともあります。
保育士が仲裁に入る際には、どうしてケンカになったのか・今はどういう状況なのかを確認してその場を整理し、子ども達で解決できるように誘導することが大切です。
また、自宅で保育園での話をすることも多くなりますが、保育士から見てお互いに非があることでも、相手が一方的に悪かったように保護者に話す子どもも多いため、ケンカがあった時には、保護者にケンカの流れやその後の様子を伝えることが大切です。

保護者対応の例
「今日お友達とおままごとで誰が何役をやるかでケンカになりました。ケンカが始まってしばらくは、全員が自分の意見を通してなかなか解決しませんでしたが、保育士が話を聞くと冷静になったのか「じゃあ私が始めは赤ちゃん役で良いから、長い針が2になったらお母さん役変わって」と言ってくれて、その後はみんなも納得して仲良くおままごとをしてい増した。時間でしっかりと役を変わることが出来ていて、とても楽しそうでした」
今回紹介したのはケンカの原因や対応方法はほんの一部で、ケンカの原因は様々なので、どのように対応すれば良いのか悩むことも多いです。
ケンカをすること自体は悪いことではなく、ケンカを通して自分たちで解決する力を身に付けることが出来るので、すぐにとめる必要はありません。
しかし、乳児や手が出やすい子の場合にはすぐにとめられる位置に移動して見守り
怪我を未然に防ぐことが大切です。
また、保護者にもケンカの様子を伝えて、保護者とのトラブルがないように配慮することも大切です。
 閲覧履歴
閲覧履歴
 最近見たお仕事
最近見たお仕事