リーダーや学年主任に求められることは?
保育園では複数担任の場合、クラスリーダーが決まっていたり、乳児・幼児それぞれにリーダーや主任が在籍している園があります。
今回は、実際にリーダーや学年主任となった場合、どのような役割や仕事があり、どのような事を求められているのかについて紹介していきます。

保育園におけるリーダー・学年主任とは
保育園によって定義が異なりますが、一般的に「リーダー」は、複数担任の場合にクラス内で1番上の立場の保育士のことを指すことが多いです。
例えば3人担任の場合はリーダーの下に中堅保育士と新任保育士がついてクラス運営を行う、というイメージです。
学年主任が在籍しない園もあれば、乳児全体のリーダー・幼児全体のリーダーを学年主任として定めている園もあります。
実際に筆者の園では、乳児フロアのリーダーと幼児フロアのリーダーの計2名が学年主任として在籍しています。
園によって方針は異なりますが、立場としては「一般保育士<リーダー保育士<学年主任<副主任<主任<園長」といった序列になることが一般的です。
リーダーに求められる役割や仕事
リーダーは複数担任の中での1番上の立場の保育士を指すことが多いことから、「クラスをまとめる」というのが、期待される役割の1つとなります。
例えば保育の考え方は保育士それぞれ異なることが多いです。
リーダーの保育士がそれぞれの保育観や考え方を聞き、意見をまとめてクラスの方針を決めたり、自ら積極的に他の保育士の意見を聞きだしたりして、円滑に保育が進むようにすることでクラスをまとめていくというのがリーダーの仕事です。
一般企業で例えると、リーダー保育士が係長、その他の保育士が一般社員という構図になります。
クラス内で何かあればリーダーの保育士が話を聞き、必要であれば学年主任や主任、園長などに報告・連絡・相談を行う中間管理職的な立場になります。
学年主任に求められる役割や仕事
学年主任は「学年をまとめる」というのが、期待される役割の1つとなります。
園にはそれぞれ理念や方針があり、それを基にして各クラスが保育方針を決めていきます。
園での理念や保育方針を達成するためには、各クラスだけの保育ではなく、他学年との連携も大切になります。
そういった場面で、乳児クラスではどのように連携をとっていくのか、幼児クラスではどのように連携をとっていくのかなど、学年での連携がとれるように積極的に提案・行動するのが学年主任に求められる役割として挙げられます。
例えばある程度人数の多い園では、夕方は保護者が迎えに来るまで乳児合同・幼児合同に分かれて自由遊びを行っている園が多いですが、自由遊びの中でもどのような遊びを行うのかを各クラスの保育士から聞き出し、意見をまとめて共有するなどは学年主任の仕事になります。
子ども達の様子から「この遊びは子ども達の反応がいまいちだった」ということもよくあるため、そういった時に積極的にフィードバックを行うのも大切です。
また、各クラスのリーダー保育士から出た意見をまとめて主任や園長に報告するのも学年主任の仕事とされる園が多いです。

リーダーや学年主任の苦労
1.後輩育成
上の立場となることで「後輩を育てる」ということが求められるようになります。
全員に同じ指導方法をしても後輩が同じように育つわけではなく、丁寧に全てを説明した方が伸びる人もいれば、ポイントを伝えて実際の保育の様子を見て学ぶ方が得意な人、実践してみた方が身に付く人など、様々です。
「丁寧に教えているつもりだけど全然育たない」など、後輩育成に対する悩みや苦労を感じている人は多い傾向にあります。
後輩育成のポイントとしては、こちらが一方的に指導するのではなく、年齢差や価値観などのジェネレーションギャップを理解し、様々な指導方法を計画・実行することです。
どうしても後輩育成がうまくいかないときには主任や園長に相談するのも1つの手です。
2.人間関係
クラスや学年をまとめることが大きな役割であるリーダーや学年主任は、人間関係に対して悩みや苦労を感じる人も多いです。
クラスで出た意見をうまくまとめられない・学年内で相性の悪い先生たちがいて雰囲気が良くないなど、様々な悩みがあります。
大切なのは自分一人で解決しようとするのではなく、周りの保育士の手も借りながらまとめていくことです。
実際に筆者が0歳児クラスのリーダーをしていた時に、同じクラスの保育士と1歳児クラスの保育士の相性が悪かったため、当該保育士以外に声をかけて、縦割りなどで同じグループにならないように協力してもらったりしていました。
午睡中の時間には保育の話しだけではなく、雑談をしながら書類をしたりすると良好な人間関係を築きやすいです。
自分一人で解決しようとすると限界があるので、周りの保育士や主任、園長にも相談しながら人間関係を築き上げていくことがおすすめです。
3.中間管理職的な立場
「リーダーだから」「学年主任だから」といった理由で、主任や園長から何かを言われたり、「先輩だから」と後輩から相談を受けたりと、一般企業で言う「中間管理職」的な立場となることが多く、上と下の板挟みになってしまうことに苦労を感じる人もいます。
筆者もリーダーを6年、学年主任を1回経験していますが、言伝などは筆者を通して伝えられることも多いです。
筆者が休みだった日の保育を見た主任や園長が、「○○先生、子どもに対しての口調が強かったから、そういう場面があったら注意してあげて」と言われたこともあります。
その時の心情としては「自分で言ってくれればいいのに」「私は口調が強いことが気になったことはないけど」「自分が休んでいたから頑張ってくれて口調が強くなってしまったのかな?」など、色々と考えてしまいます。
そういった中間管理職的な立場から心が疲れてしまうという人も多いため、大切なのは真面目になりすぎないことだと感じています。
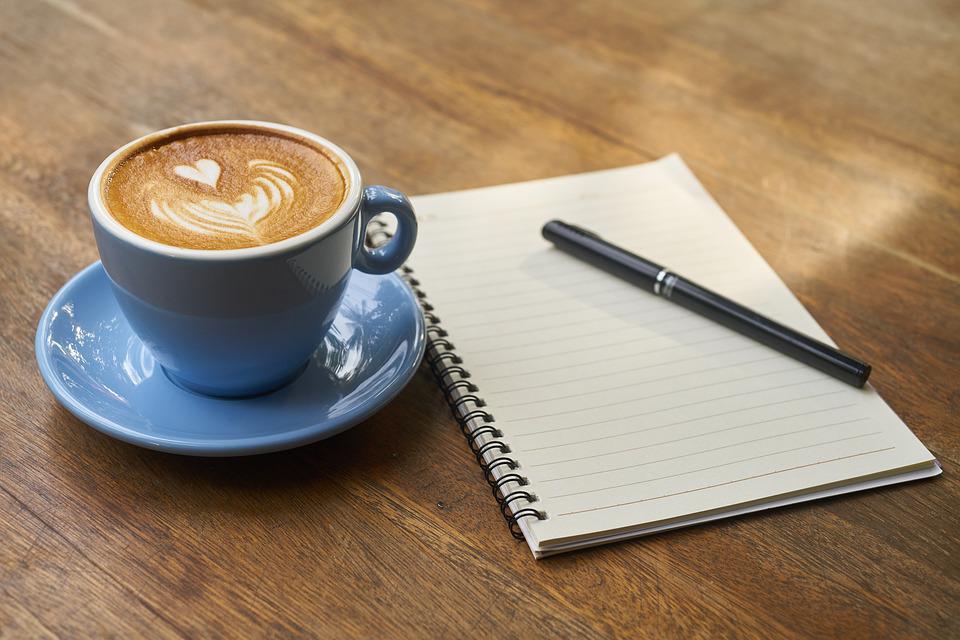
リーダーや学年主任になると求められる役割や仕事も増えて大変ですが、その分「信頼・評価してくれている」という自信にも繋がります。
責任感を持って仕事をすることはもちろん大切ですが、自分だけで解決しようとするのではなく、必要に応じて周りの保育士や園長、主任にも助けてもらいながら、自分1人で抱え込まないことが大切です。
 閲覧履歴
閲覧履歴
 最近見たお仕事
最近見たお仕事