保育園での事故多発!コロナ渦になって増えた気がするけど、、、
子どもは大人が想像もしないような行動をしたりすることから、保育園で事故が起きてしまうことがあります。
しかし、コロナ渦になって事故が増えてきています。
なぜコロナ渦になり事故が増えているのか、また、どうすれば事故を防ぐことができるのかについて紹介していきます。

コロナ渦で事故が増えた理由
コロナ渦で事故が増えた原因として考えられる大きな理由は、消毒作業に人手をとられてしまっているというのが挙げられます。
玩具やドアノブ、手すりなどの消毒作業がコロナ渦前よりも増え、清掃担当の職員が在中していない園では保育士が消毒作業を行う必要があります。
午睡中は書類や会議などで忙しく消毒作業を行う時間がとれずに、子どもをみながらの消毒作業を行っているという園も多く、子どもを見ているつもりでも、作業をしながらでは目が離れてしまうことも多く事故に繋がるというケースが多いです。
また、新型コロナウイルスに感染したり、濃厚接触者として自宅療養・自宅待機期間があることで現場の人手が足りないといったケースや、コロナ渦で子ども達もストレスが溜まっていて、遊び方などが乱暴になってしまい事故に繋がるケースもあります。
事故の事例と対策方法
保育園で多い事故と共に、対策方法についても紹介していきます。
1.誤嚥
玩具を口に入れて飲み込んでしまう・食べ物がのどに詰まってしまうという事故です。
玩具の誤嚥は乳児に起こりやすい事故ですが、食べ物に関しては幼児でも起こり得ます。
2020年には、4歳児が幼稚園の給食で提供されたブドウや節分の豆をのどに詰まらせて死亡してしまった事故が立て続けに起きています。
対策方法
玩具に関してはサランラップの芯を通るサイズの玩具は誤嚥の危険性があるため、小さい玩具は乳児クラスでは出さないようにすることで誤嚥を防ぐことができます。
玩具を用意する際には必ず大きさを確かめ、サランラップの芯を通らないサイズのもので遊ぶようにすることが大切です。
ブドウやミニトマト、白玉だんごのような丸くてつるっとした食べ物はのどに詰まりやすく、大きさ的にも気道をぴったりとふさいでしまうサイズのため、小さく切って提供することが大切です。
切り方としては4等分以上に切ることがおすすめです。
半分に切った場合、1つの大きさは小さくなりますが、円の直径は切る前と変わらないため誤嚥の可能性があります。
4等分以上に切ることで円の直径が小さくなり、誤嚥の可能性が低くなります。
また、餅や豆などののどに詰まりやすいものは保育園では提供しない、リンゴや梨などの固いものは薄くスライスするなど、給食室の職員と連携をとりながら相談して子どもの事故を防ぐことが大切になります。
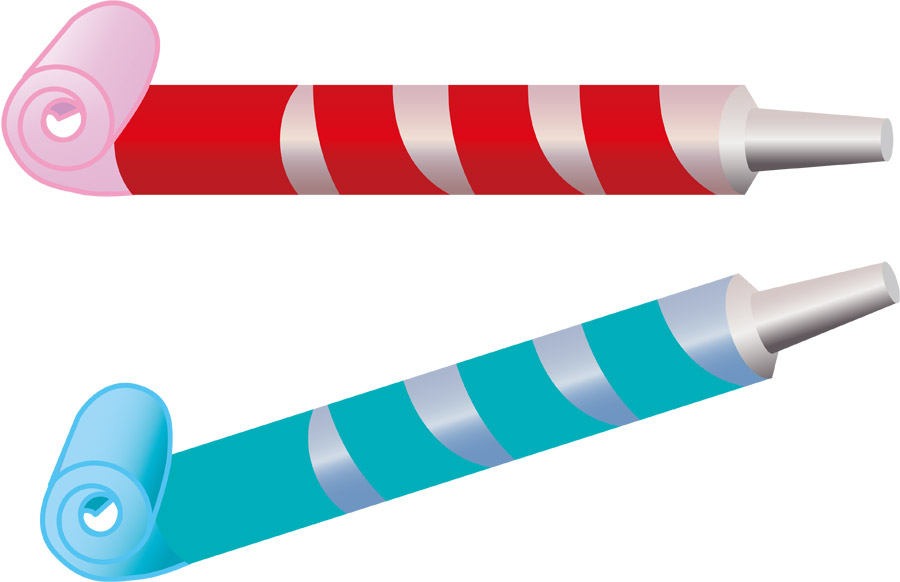
2.窒息
上記で説明した誤嚥も窒息の原因の1つですが、他にもフードや洋服・袋・縄跳びなどの紐、よだれかけなども窒息の原因となり、保育園で起こりやすい事故の1つです。
また、乳児ではミルクの吐き戻しや寝返りができない子どものうつぶせ寝なども窒息の原因となります。
対策方法
危険な洋服については、配布物や掲示を通して保護者に危険性を伝えて保育園には着用してこないように協力してもらうことが大切です。
例えばフードや紐付きの洋服であれば、フードが引っ掛かって首がしまってしまう危険性があることの具体例を挙げて説明することで協力してもらいやすくなります。
また、巾着袋などの紐を首にかけて遊んでしまう子や、縄跳びを首にかける子もいます。
着替えなどで巾着袋を出す場面や縄跳びを扱う場面では子どもから目を離さず、首にかけようとした時にはすぐにとめることが大切です。
乳児では午睡時間の窒息が多く、食後にあおむけで寝かせていた際にミルクを吐き戻して窒息したり、うつぶせ寝による窒息が起こりやすくなります。
ミルクを飲みながら寝てしまった時などは保育士の傍にベッドを置き、しばらくの間顔を横向きにして寝かせて吐き戻しても大丈夫なようにすると安全です。
また、よだれかけが顔にかかってしまう、手に引っ掛かって首がしまってしまう可能性があるため、午睡の際にはよだれかけは必ず外します。
うつぶせ寝はSIDSにも繋がるため、年齢を問わずうつぶせ寝をしないようにする、0歳児は5分、1歳児は10分、2歳児は15分おきに午睡チェックを行うことで窒息を防ぐことが出来ます。
3.転倒・転落
散歩中に転んで膝をすりむく程度の転倒であれば日常的な怪我ですが、転倒した先がブロックの角で頭やおでこを縫うような怪我になったり、階段や遊具からの転落は大きな事故となります。
保育士不足により保育士の目や手が足りないと起こりやすくなります。
また、人手が足りずに保育士の心に余裕がないと、普段なら予測出来る危険も見逃してしまいやすくなります。
対策方法
保育士の数が足りないときには無理に戸外に出ないことで、転倒や転落の危険性を下げることができます。
また、日頃から事故にはつながらなかったが危なかった「ヒヤリハット」を基に、危険予測を立てておくことが大切です。
例えば「この公園はこの遊具が危ないから保育士が必ずつくようにしよう」や、「この場所が死角になりやすいから注意して見るようにしよう」などと、普段から遊ぶ場所での危険予測を行うことで事故を防ぐことに繋がっていきます。
また、人数の少ないクラスや保育士に余裕のあるクラスがあれば、縦割り保育の要領で子どもを数名他のクラスへお願いするというのも1つの手です。
月齢の低い子は下のクラスへ入れてもらうことで無理なく生活ができたり、月齢の高い子は上のクラスへ入れてもらうことで更なる成長を促す効果も期待できます。
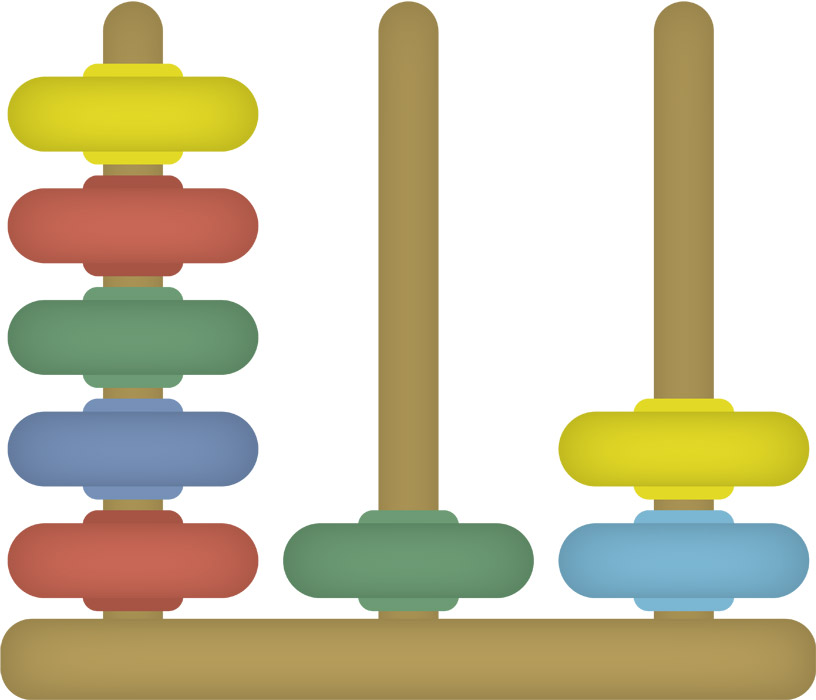
新型コロナウイルスが流行して2年以上が経ちました。玩具や施設の消毒、感染症対策の徹底など、これまでにはなかった仕事も増え、自宅療養や自宅待機期間により保育士不足が深刻になっています。
人手が足りなくなることで事故が増えやすくなるため、今回紹介した保育園で起こりやすい事故について理解をし、どのように保育をすれば防ぐことができるかを考えることで、大きな事故を防ぐことにつながっていきます。
子どもたちが安心・安全に保育園生活を送れるように、今回紹介した内容を参考に、保育園での事故について考えてみてくださいね。
 閲覧履歴
閲覧履歴
 最近見たお仕事
最近見たお仕事