加配かも、、、?保護者の方への話し方!
子どもが他の子どもと同じように集団生活を送ることが難しい場合に、加配が必要かどうか検討する場合があります。
加配制度について説明しながら、加配の子が保育園で過ごしやすくなるための援助方法や、保護者への接し方について紹介していきます。

加配制度とは
加配制度とは、他の子どもと同じように集団生活を送ることが難しい場合に個別に保育士がつき、生活の補助や集団への参加をサポートしていく制度のことです。
保護者からの申請によってだけでなく、園独自で加配を行うことができます。
障害児保育と異なる点として、障害児保育は障害者手帳の保持者や、特別扶養児童手当の受給者、その他医師からの診断を受ける必要があり、自治体によって必要書類があります。
一方で加配制度では、保護者の不安感であったり、保育士が実際に保育を行う上で集団生活が困難だと感じた場合に加配保育士をつけることが可能です。
障害児保育では明確な診断が必要となりますが、加配ではいわゆる「グレーゾーン」と言われる子どもに対しても保育士をつけることが可能となります。
つまり、診断は特についていないが集団生活に困難を感じている子どもが、安心して無理なく過ごすために活用することができる制度ということになります。
加配の子が保育園で過ごしやすくなるために
実際に加配が必要な子どもが保育園で過ごしやすくなるために、保育士はどのように援助していったらいいのかを紹介していきます。
1.生活に関する援助
排泄や着替え・食事など、生活に関する援助を行うことで、子どもが園生活を送りやすくしていきます。
加配の子の中には、食具の持ち方や着替えの方法など、覚えるまでに時間がかかる子も多いため、丁寧に繰り返し伝えて身に付けていけるようにすることが大切です。
また、好き嫌いが多く偏食の子もいるため、給食の量を調節しながら少しずつ食べられるようにしていくなどの援助も大切です。
2.他児との関わりに関する援助
加配の子の中にはうまく友達と関わることが出来ずにトラブルになってしまう子も多いため、他児との関わり方を伝えていくことも大切な援助の1つです。
意地悪をしようと友達とトラブルになるのではなく、友達と遊びたい・見てほしいなどの理由があるにも関わらず正しい関わり方がわからずにトラブルになってしまうことがほとんどのため、どうしてそういう関わり方をしてしまったのか理由を聞き、その時にはどのように関わればよかったのかを繰り返し伝えていくことが大切です。
また、話の理解が難しい子どももいるため、絵カードや写真などを活用するなど、どうしたら子どもが理解しやすいのかを考えて援助していくことが必要です。
3.集団参加に対する援助
保育園によっては一斉活動を行っている園もあり、製作の時間・集団遊びの時間などと時間が決められている場合があります。
そういった集団活動に無理なく参加できるように援助を行っていくことが必要です。
特に製作の工程の説明やゲーム遊びにおけるルールの説明などを理解することが難しい子も多いため、隣で見本を見せながら丁寧に伝えていくなどの個別援助が大切です。
また、子どもが嫌がる時には5分だけ・1回だけなど、時間や回数を決めて少しずつ参加できるようにしていくなどの対応も必要です。
4.保護者との連携
保育園での様子を保護者に伝えながら、家庭ではどのように過ごしているのか・どのような姿なのかを聞き取り、園でも安心して過ごせるように援助をしていくことが大切です。
また、食事や着替えなどは家庭での協力も不可欠なため、園ではどのようなことに力を入れていて、どのような援助をしているのかなど、詳しく伝えて同じように援助してもらえるようにすると、子どもの身に付きやすくなります。
例えば正しい食具の持ち方を伝える場合、「園では「手をバンバンして」と伝えて鉄砲の形を作ってもらい、そこからフォークを乗せて正しい持ち方で持てるようにしています。また、途中でフォークを握ってしまうこともありますが、何度も伝えて嫌にならないよう、1回の食事で3回までと決めています」というように、園での様子を細かく伝えていくことが大切です。

加配が必要な子どもの保護者への接し方
保護者から不安を感じて加配をつけている場合は、園での子どもの様子や援助方法を伝えていくことでスムーズに連携がとれますが、保育士が保育を行う中で加配が必要だと感じた場合に保護者にどのように伝えていくかについては難しい問題でもあります。
話し方を間違えると「うちの子が普通じゃないってこと?」と保護者が傷ついたり不信感に繋がる可能性があります。
そのため、保護者に子どもの様子を伝える時に気を付けたいポイントについて紹介します。
1.園での様子を相談事として伝える
「集団遊びに入るのが難しいんです」「友達とトラブルが多いです」などと伝えると、保護者が傷ついてしまうことがあります。
そのため「園では使いたい玩具がある時に言葉で伝えることが難しく、手が出てしまうことがあるのですが、園では思いが通らない時にはどういった様子ですか?」と、自宅での様子や対応方法を聞いてみる伝え方がおすすめです。
きょうだいがいない場合には他児との関わりが自宅では見られずに落ち着いて過ごしている場合もあるため、「こういった姿があり、このように伝えてはいるのですが、お母さまのおすすめの対応方法などありますか?」など、一緒に対応を考えてほしいと相談することが大切です。
2.経過を伝えていく
園での気になる姿を保護者に伝えたあとは、経過を伝えていくことが大切です。
「この前ご相談させていただいた対応をしていて、今はこのような姿です」というように、現在の様子について説明します。
改善がみられた時にはすぐに報告すると保護者の不安を取り除くことができます。
特に様子に変化がない場合には1か月に1回ほど経過を伝えていくことで新たな対応などを考えていくことが出来ます。
3.子どものためだということを丁寧に説明する
対応を変えても改善の様子がなく、加配をつける方向で話が進んだ時には保護者に子どもの様子を丁寧に伝えながら、加配を付けることにおける子どものメリットを伝えていきます。
例えば「ご相談させていただいてから様々な対応をしてきましたが、やはり集団に入ることが難しいことが多いです。そのため、集団遊びを行う際などにはもう1名保育士に入ってもらい、集団遊びへの参加が難しい時にはその保育士に対応してもらい、○○くんが無理なく過ごせるようにしていけたらと思っているのですが、どうでしょうか?」と言うように
丁寧に伝えることで、子どものためならと納得してもらえることが多いです。
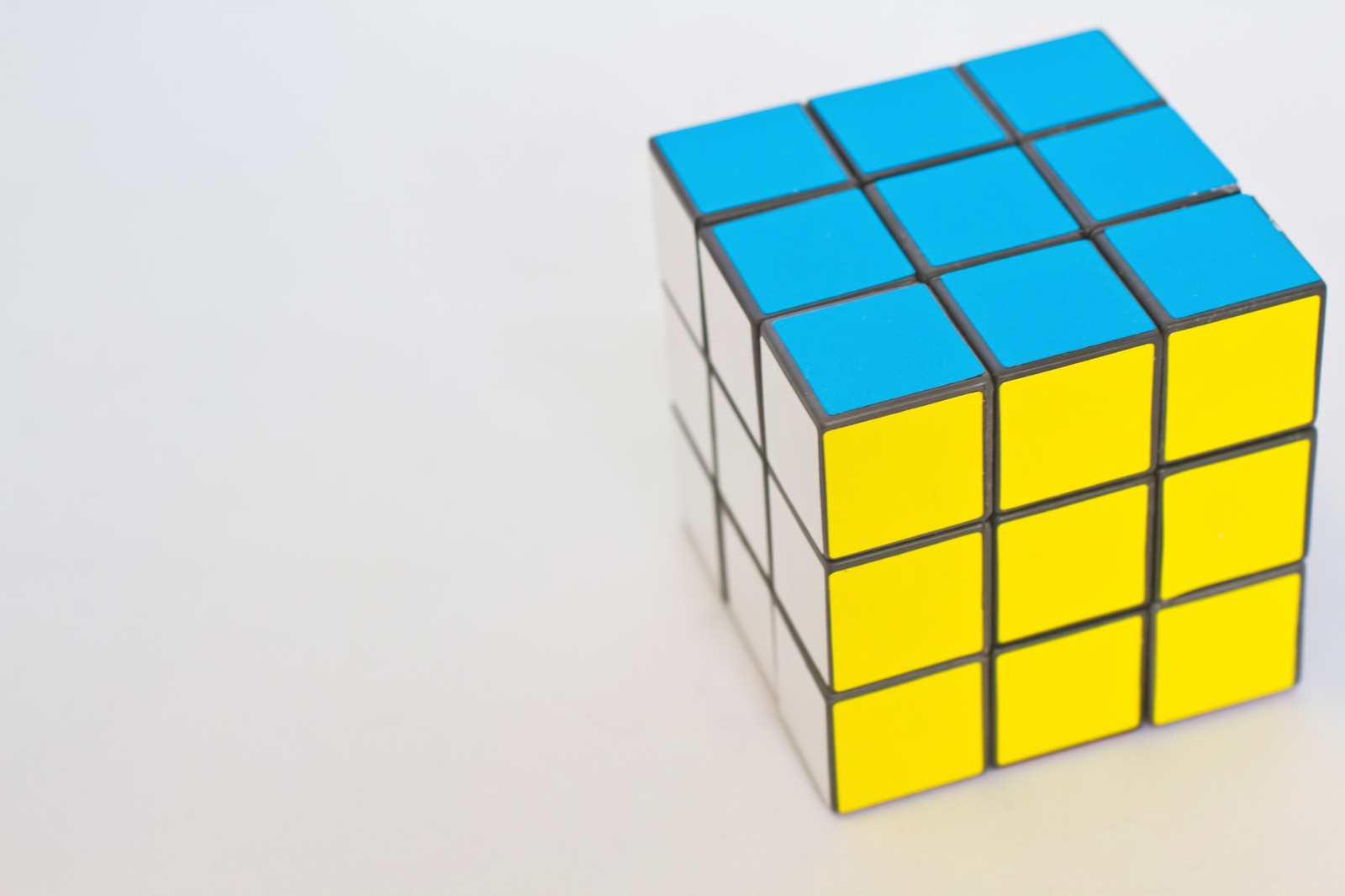
加配が必要な場合は子どもの援助や保護者との関わりなど、心配事も多いですが子どもが安心して無理なく園生活を送るために必要なことでもあります。
加配が必要かもしれないと考えたときには、今回紹介した内容を参考にしてみてくださいね。
 閲覧履歴
閲覧履歴
 最近見たお仕事
最近見たお仕事