排泄間隔の短い子ども、トイレに連れていきたいけど人手が、、、
2~3歳ごろになると、トイレトレーニングを始める子も多いですよね。
トイレトレーニングが軌道にのるまでは排尿間隔が短く、他の子どもの保育を行いながらトイレに連れていくことが人手的に難しいと感じてしまうことがあります。
今回は、トイレトレーニングの進め方や、人手不足の中でトイレトレーニングを行うための工夫などについて紹介していきます。
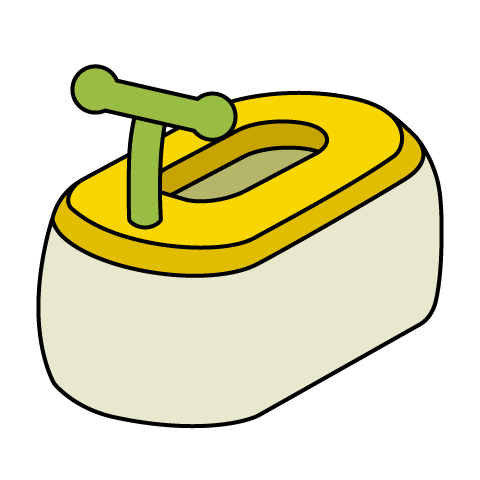
トイレトレーニングを始めるタイミング
トイレトレーニングを始めるタイミングは子どもの排尿の様子によって異なりますが、2歳児クラスあたりがトイレトレーニングを始める子が多い傾向にあります。
トイレで排尿できることが増えてきたら、保護者に園での様子を伝えてパンツを用意してもらい、園でもトイレトレーニングを始めていくのがおすすめです。
また、季節としては寒い季節よりも暖かい季節が始めやすいです。
汗で水分が出てしまうため、排尿感覚が冬に比べて長くなりやすい傾向にあります。
トイレトレーニングの進め方
基本的なトイレトレーニングの進め方について紹介します。
1.保護者と園での様子を共有して始める
「トイレトレーニングを始めようと思います」と伝えるのではなく、「最近トイレでの排尿が増えてオムツが濡れていないことが多いので、そろそろトイレトレーニングを始めてもいいのかな?と思っています。お家での様子はいかがですか?」というように、園での様子を伝えながら自宅での様子や、保護者の意見を聞いて進めることが大切です。
トイレトレーニングは家庭との連携が必須で、自宅で何もトイレトレーニングをしてくれないと、スムーズに進んでいかないことが多いので、家庭でもトイレに促してほしいこと、パンツにも挑戦してみてほしいことをお願いする必要があります。
また、園によって方針も異なりますが、トイレトレーニングを円滑に進める際にはトレーニングパンツよりも、通常の布パンツでトレーニングを始めることがおすすめです。
トレーニングパンツは4重・5重などにしてズボンや床がぬれにくい構造になっています。
自宅で余裕のない時には床を拭く手間などが省けて便利なのですが、子どもがパンツが濡れた不快感を味わいにくいというデメリットもあります。
「パンツが濡れたら気持ち悪い=トイレで排尿をする」ということが子どもの中で出来てくると、自分からトイレに行けるようになることにも繋がるため、パンツを用意してもらう時には布パンツをお願いすることも1つの手です。
2.子どもの排尿感覚を把握する
始めのうちは保育士が子どもの排尿感覚を把握し、感覚に合わせてトイレに誘うことが大切です。
例えば30分間隔の子どもであれば、25分ほどしたらトイレに誘ってみて、出なければ10分程時間をおいて再度誘ってみるなどの援助が必要です。
出たときには褒めて自信につなげ、失敗してしまった時には怒らず「パンツが濡れて気持ち悪いね。次はトイレでおしっこしようね」と声をかけることが大切です。
3.排尿感覚をのばしていく
30分間隔で安定してトイレに行けるようになったら、自分でトイレで排尿する力がついてきているため、排尿感覚を少しずつのばしていきます。
始めは10分程度声をかける時間を遅くし、大丈夫であれば更に10分と、少しずつのばしていくことで、膀胱に尿を溜められるようになっていきます。
4.自分でトイレにいけるようにする
散歩前や給食前などは集団でトイレに誘う事も多いですが、朝・夕の自由遊びの時間などは個別にトイレに誘う事も多いです。
そういった時間にあえて保育士から声をかけず、「トイレに行きたくなったら教えてね」と伝える事で、自分でトイレに行くという習慣を付けていきます。

人手が足りないときにトイレトレーニングを進める工夫
排尿間隔がバラバラだと、他の子どもの保育を進めながら個別にトイレへ連れていくことが難しい場合があります。
人手が足りないときにできるトイレトレーニングの工夫について紹介します。
1.担当制を取り入れる
だいたい同じくらいの排尿感覚の子どもでグループを作って担当を決める事で、まとめてトイレに連れていくことができます。
オムツの子どもや排尿間隔の長い子は散歩前や給食前、午睡の前後などの生活の節目でおむつ替えやトイレへ行き、感覚が短い子は20~30分に1度トイレへ連れていくなど、まとめてトイレへ連れていく事で人手が足りない中でもトイレトレーニングが進めやすくなります。
また、人手が足りない場合、排尿間隔が20分以下の子どもは排尿間隔が伸びてくるまではオムツで様子を見て無理には進めないというのも1つの手です。
2.室内遊びを取り入れていく
戸外遊びの際に排尿間隔が短い子どもがいると、おもらしの対応や公共のトイレの使用などで人手が足りなくなってしまうことが多いため、すぐにトイレに行ける園庭や室内遊びを取り入れながらトイレトレーニングを進めることがおすすめです。
また、人手が足りない中で公園に行くときには、無理せずオムツを履くことも大切です。
3.日々の保育の中でトイレの座り方や着替え方が身に付くように援助する
2~3歳児であれば、正しい座り方が身についている場合トイレに1対1で着いていく必要がなくなります。
勿論声をかけたり、きちんと拭けているかなどの援助は必要ですが、日々の保育で正しい方法が身についていれば、保育士が目に入る場所にいれば付きっ切りで援助をする必要はありません。
室内で遊んでいる場合、トイレに座れた事を確認したら他の子を見ながら「出た?」と声をかけたり、排泄が終わったら保育士が見れる位置で自分でパンツやオムツを履いてもらう事で、人手不足の中でもトイレに誘うことは可能です。
そのためには、日々の保育の中でしっかりと援助を行っていくことが大切です。
人手が足りない中でトイレトレーニングを進める時の注意点
人手が足りないと保育士の心の余裕もなくなることが多いため、失敗してしまった時に「何で言わないの」「だからトイレに行ってって言ったのに」などと、子どもを怒ってしまう可能性が高くなります。
子どもは精神的に不安定になるとおもらしをしやすくなる子どももいます。
筆者の長女も今までおもらしをほとんどせずに過ごしていたのに、次女が生まれてから1ヶ月程はおもらしが続いたり、担当していた子どもが引っ越しのあとしばらくおもらしが続いたりする経験をしています。
そのため、子どもが安心してトイレトレーニングを行えるような環境作りが大切です。
どうしても人手が足りないようであればその日はオムツで過ごすというのも1つの手です。
子どものトイレトレーニングを進める時には、子どもを責めたりせず、無理なく進めていけるような環境作りが大切です。

人手が足りないと、「そろそろトイレに連れて行ってあげたいけれど、この場を離れられない」というもどかしさを感じてしまうことがあります。
今回紹介した内容を参考にしながら、子ども達が無理なくトイレトレーニングを行えるような工夫をしてみてくださいね。
 閲覧履歴
閲覧履歴
 最近見たお仕事
最近見たお仕事