こんな保育園もあるんだ!ユーモアたっぷりの保育園をご紹介♪
保育園によって保育方針が決まっていて、働く保育園によって保育内容や行事、働き方が大きく異なります。
今回はユーモアたっぷりの保育園を紹介していきます。

ユーモアたっぷりの保育園
ユーモアたっぷりの保育園を、園の特徴と共に3園紹介します。
1.どろんこ保育園
保育研修などに行くと聞くことも多い保育園です。
毎日の座禅や雑巾がけ、畑仕事や縁側給食など、珍しい活動を数多く取り入れています。
身に付く6つの姿として、
- 怪我をしない強い体を育てる
- 自分で出来ることを自分でする
- 全ての人との関わりから判断・行動を身に付ける
- 活動を選択し、自分で考えて行動する
- 生死を知る
- 感じたこと・考えたことを表現する
ということを挙げています。
散歩時以外は室内・屋外問わずはだし保育を行うことで足指で地面をつかむ力を身に付けたり、雑巾がけを通して転んだ時に自分の身体を支えられる身体作りをしています。
また、日の出ている間は基本的に戸外活動の園なので、朝に座禅を取り入れて静の時間を取り入れる活動も行っています。
他にも、食事の盛り付けや配膳は子ども達が自分で行ったり、冬には焚火をするなどのユニークな活動も行っています。
2.オルト保育園
2階・3階建ての保育園の場合、多くは階段を使って移動しますが、オルト保育園では1階から3階までを植物のツルに見立てたスロープで移動することができます。
スロープには子どもの目線に丸窓がついていて、移動中に各階の子どもに手を振ったり様子を見たりすることもできるデザインとなっています。
給食がバイキング形式であったり、月に1度誕生月の子には「すてきな食卓」という普段とは違う特別なランチが提供されるのもユニークなポイントです。
オルト保育園の1番のポイントがアトリエです。
子ども達が自由に使える画材や素材を用意しており、アトリエ内だけでなく、持ち出して製作することもできるようになっています。
3.さくらぎ保育園
敷地内に、園庭・中庭・サンデッキ・サンテラス・ひろいっぱらという5つの園庭を設けており、どの保育室も園庭や中庭に面しているため、開放感のある作りとなっています。
給食はセミバイキングとなっていて、子どもが自分で食べる量を調節できます。
また、ランチルームという場所が設けられており、ランチルームで異年齢児との交流をもちながら食事ができるのもユニークなポイントの1つです。
幼児では毎週金曜日に体育指導を行っていたり、5歳児では茶道を月に2回行っています。
茶道を行っている園は少なく、茶道を通して礼儀作法やゆとりのある心づくりを行っています。

特徴のある教育方法
特定の教育方法を取り入れて保育を行っている園も多いです。
保育の方針が決まっているため、自分のしたい保育を行うことは難しいことも多いですが、自分の考える保育観と合っている保育園を選ぶと働きやすいというメリットもあります。
今回は特徴的な教育方法をつ紹介します。
1.シュタイナー保育
シュタイナー保育とは、子ども達一人ひとりの個性を大切にして、自由な子どもを育てるという人間形成を目標とした保育のことです。
人間は7年ごとに成長の節目を迎えると考えられており、0~7歳では「身体の感覚を健全に育む」という点を重要視しています。
シュタイナー保育を取り入れている園では、天然のものにこだわりがあり、井戸を設置する
・無農薬野菜を使う・木の玩具を使うことに力を入れている園も多いです。
また、四季を大切にしており、七夕には染物をしたり、秋には収穫祭、冬にはミカエル祭などを行っている園も多くあります。
2.ヨコミネ式教育法
ヨコミネ式教育法とは生まれ持った可能性を最大限に引き出すという理念の元、子ども達の自立を目的とした教育方法のことです。
テレビでも取り上げられていることが多く、目にしたことがあるという方も多いと思います。
基礎能力や基礎体力、感性を育むことに力をいれており、読書や絵画、鉄棒や跳び箱、逆立ちなどを積極的に取り入れている園が多いです。
厳しいイメージを持つ方も多いですが、保育士は子どものやる気を引き出す環境を作って怪我のないように見守ることで、頑張る気持ちや友達同士で助け合う心を育むことができます。
鉄棒や逆立ちなどに力を入れているので、運動が好きな方の方が楽しんで保育に参加できます。
3.モンテッソーリ教育
モンテッソーリ教育は、子どもの自己教育力を向上させることを目的とした教育方法のことです。
近年、家庭での育児に取り入れる方も多く、一度は耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
モンテッソーリ教育を取り入れている園では、指先の発達を促す遊びや、図形や数、色への理解を深められるような活動を多く取り入れています。
指先の発達を促す遊びとしては、ひも通しや縫いさし、あけ移しなど、図形や数の理解では、図形合わせや色合わせなどを行っていることが多いです。
専用の教具を使って保育をすることで、生きる力を感覚的に育むと考えられていて、一人一人が興味のあることにじっくりと取り組むことができます。
指先遊びや図形や色への理解など、室内での活動にも興味がある方におすすめの教育方針です。
4.レッジョ・エミリア教育
レッジョ・エミリア教育では、子どもの主体性を大切にし、一人一人の個性を引き出すことを目的とした教育法です。
子ども達の発想を大切にして子ども主体の保育を行ったり、ドキュメンテーションを活用して活動を記録したりする保育園が多いです。
子どもの興味があることや発想から活動を設定していくため、「電車が好き→電車を見に駅へ行く→電車を作ってみる→発展させて駅や街も作る」というように、長期的に同じテーマに合った活動を行うという園が多く、子どもの興味が広がるように声掛けや援助をすることが大切とされています。
子どもの個性を伸ばしたい、興味のあることをとことんやらせてあげたいと考える方におすすめの教育方法です。
ユニークな活動や教育方法を取り入れている園は数多くあり、自分の保育観と合っているのかを考えることが大切です。
また、様々な園や教育方法を知ることで、今の自分の保育園ではどのようなことなら取り組めるのか、どのような活動であれば子ども達が楽しめるのかなど、部分的に活用することも可能です。
いいところは参考にしてみることがおすすめです。
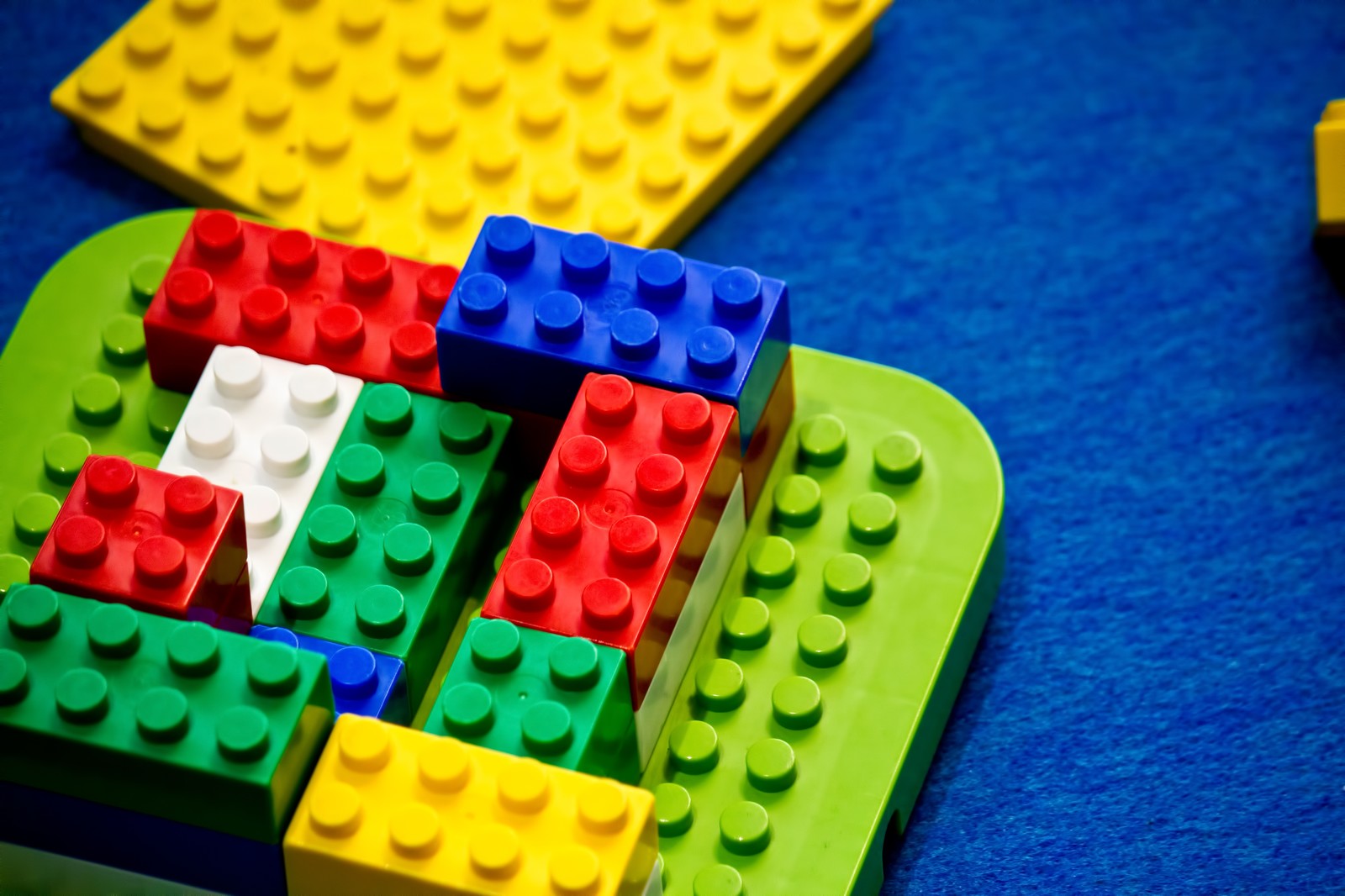
 閲覧履歴
閲覧履歴
 最近見たお仕事
最近見たお仕事